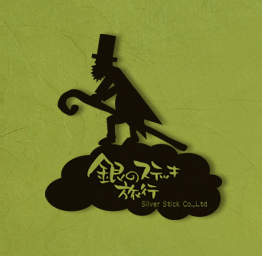ポーランド、添乗員報告です
「来月はポーランドに行きます」
保険会社の方に、そう伝えると
「へえ、ポーランドって何がありましたっけ?」
私にとっても初めての訪問となったポーランド。
添乗員レベルのにわか勉強で、少しは理解をしながらも、その実、
「確かに何があるんだろう…」が本音。
世界史を専攻しながら、たぶん近代史に入るくらいで授業は何となく受験仕様に移り、
第二次世界大戦あたりで、尻切れトンボ。
そう、うやむやに歴史は終わっていました。
もちろん、授業のことですが。
私のなかのポーランドは、「アンネの日記」や「シンドラーのリスト」から知る、
踏んだり蹴ったり、灰色の空だけが植えつけられていて、
何十年たった今も暗い印象を持ったまま添乗に出ていました。
10月のポーランドはすっかり冬支度と思い、
着ぶくれして到着したものの、思いがけず晴天、温暖な天気に恵まれ、
突き抜けるような青空の日々となりました。
コペルニクス生誕の地・古都トルンや、
妖精像がお出迎えの水都ヴロツワフや、
世界遺産に世界でも最初に認定された美しい古都クラクフなど、
皮肉にも多文化様式の独特な建築景観を残していました。
このまま終わることもできた旅です。
ポーランドに若かりし頃、音楽の公演会で訪ねたという方が仰いました。
「アウシュビッツに行くべきだった」
「でもあの時、私たちには選択権があったから
私は迷わず行かない方を選んだのよ」
 古都クラクフから、車で2時間ほど走った町オシフィエンチムに、
古都クラクフから、車で2時間ほど走った町オシフィエンチムに、
かつてあった強制収容所「アウシュビッツ」。
その日も、雲ひとつない透明な空が広がっていました。
ガイドさんの熱心な説明を受けながら、
まぎれもなく人間の作り出した不条理なレールを私たちも歩いてみました。
一直線に続く、選択という言葉のない道です。
どの展示室も手を強くつねって顔を上げていないと、
とても平常ではおれませんでした。
でも、一度だけ、その行為をしたところで、
どっと崩れそうになる感情の隆起を抑えることができない場面がありました。
それは、鍋です。
ここに連れられてきた人々には未来があった。
生活を続けるというシンプルな未来が。
どんな料理を作るつもりだったのですか。
今、私の家の台所にもある同じ取っ手のついたものや、
そうでないものや、鍋が大量に展示されていました。
おびただしい数の鍋や食器類。
そこに日常という希望があったのです。
使われることのないまま、今、目前に積み上げられた無言の鍋山の塊が、
怒涛のように胸を衝きあげてきました。
さらに、子供たちが収容されていたという施設跡に入った時です。
言いようのない違和感を覚えたのです。
それが何であったのか、これは帰国後しばらくして気づきました。
子供部屋、といっても三段ベッドが劣悪な環境下に所狭しと詰められただけの小屋。
その部屋の壁に子供向けのマンガが描かれていたのです。
しかも私の記憶が確かなら、
外国人がイメージする宮廷帽子をちょこんと被った
中国の子供が東洋らしき風景の中で遊んでいるという絵でした。
クマさんでも、リスさんでもいいはずなのに。
つまり、この環境下で、まだ見ぬ世界、異文化への憧れ、
そんなことを想像させるに値する絵だったのです。
その絵があるだけで、明日があるように錯覚できたのです。
ガイドさんの言葉が忘れられません。
「皆さんのように熱心に耳を傾けて下さる方には、
私も熱が入ってしまいます。でもそのたびに、この事実に向き合うことになり、
しばらく疲労困憊に陥り、寝込むこともあります」
恐ろしくオレンジ色に染まる真ん丸な落日を横目に、
皆さん、それぞれの時間を過ごされました。
沈黙のなか。
不謹慎にも、私はお腹がグウグルと鳴りだして、
今日の晩ごはんは何だったかと、行程表を手にして、「七面鳥だ!」
誰からも遮られることのない、間もなくおとずれるはずの「絶対の時間」、
ディナータイムを思い、安堵のなかで目をつむることにしたのでした。
2017年10月16日~24日 ポーランド