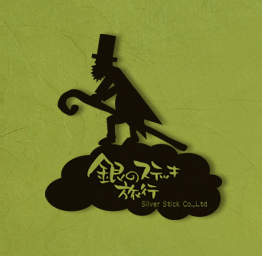山伏の寺の怖い話
つい数日前まで、財布のなかにはけっこうなお札が入っていたはずなのに、
食べて、飲んで、おなかが減ったらまた食べて飲んで、をくりかえしていたら、
とうとうすっからかんになってしまいました。
そのときに思い出したのが、先週、三木へのツアーで訪ねたこのお寺。
伽耶院(がやいん)、といいます。
毎年10月10日には、西日本一円から
二百名近い山伏が集うという修験道の寺。

門をくぐってすぐの立て看板には、「入山料、おひとりにつき草引き十本」の文字。
この日は特別にお願いして本陣のなかに招き入れていただき、
ご住職よりじきじきにお話を伺いました。
「この寺は山伏の寺ということになってますが、山伏という職業があるわけやありません。
皆さん、ふだんはご商売してたり、会社勤めしてたり、学校の先生やったりしてはる人たちです」
外はぽかぽか陽気なのに、本堂のなかはひんやり薄暗く、そこに響くご住職の声。
「修験道では年に何度か、大峯詣りいうのをします。
奈良の吉野から20㎞ほど先の大峯山まで、背骨のように走る山脈を数日かけて歩くんです。
一日二日なら、誰でも歩ける。
でも三日四日すると、足が動かんようになります。
なんのために、そんなしんどいことするかいうたら、
自然の真ん中に身を置くことで、ふだんの生活と違う、異次元を感じるため、いうことになりますかなぁ。
起床は3時、出発は4時。
昼めしに持って歩ける弁当も決まってまして、
にぎりめし二つと塩こぶひとかけら、梅干しひとつ、これだけです。
朝の4時に歩きはじめますから、8時にはもう腹が空きます。
そこでまず、握り飯をひとつだけ食べていい。
また歩いて、今度は昼ごろ、もうひとつの握り飯を食べるんですが、
そこでぜんぶ食べてしもうてはいけません。
必ず、半分、残しておく。
というのも、その日の小屋に入る手前に、必ず、足がかからんほどに急な坂なり崖がある。
見ただけで、足がひるむ。
そこへ向かう前に、必ず腹のなかに何か入れんと体が動きません。
そのときのために半分のこしておくんです。
なかには腹がもたんと、ほとんど食べてしもてる山伏もいる。
それでも必ず、米の数粒は残してあります。
それが、自分はまだ食べ物を持っている、という支えになる。
米のわずか数粒に、塩こぶのかけら。
そして梅干しの種。
もういっぺんしゃぶったら、ちっとは味がするかもわからん。
そんなもんでも、まだ食べ物があるという気持ちの支えになるんですなぁ。
そんなとき、山伏どうしで話しますのんや。
こんな話、家に帰って嫁にゆうたところで、とうてい信じてもらえへんやろなあて。
山での米数粒、あれを食べ物というんなら、
家でふだん食べてるもの、あれはいったい何なんやと。
家では、きのう炊いた飯? そんなん犬にくれてやれ、てなもんですやろ。
なに、犬も食わへん? そんなら捨てたらええやないか、とこうなる。
歩きどおしやから、もちろん、のども乾く。
そんなときは、山のなかの、落ち葉の間にわずかに溜まった水を飲む。
ボウフラもわいてます。
それでもこうやって掬うて、手のなかのボウフラに、悪いなぁ、ごめんなぁ、言いながらそれを飲む。
その水で、生き返るんです。
これが水なら、あのふだん飲んでる水は何なんやいうことです。
水道の蛇口ひねったら、ジャージャー水が出る。
水が出えへんかったら、水道局に電話して文句いう。
ほしたら、水道局の人はすんません言うて謝りますやろ。
あの水は、いったい何なんやと…」
皆さんがどう感じられたかは分かりません。
でも、私はなんだか怖かった。
大峯詣りの厳しさが、ではありません。
ご住職のおっしゃるように、それが水で、それが食べ物なら、
ここ数日、気前よくお札と引き換えに、
私が飲み食いしていたものは、いったい何だったのでしょう。
だいたい、何を飲んで何を食べたのかすら、あまり覚えていないのです。

※銀ステバザーのお知らせ
3/25(金)~27(日) 10:00~17:00
会場:銀のステッキ内
みなさまのご来店をお待ちしております。
詳細は、こちら、、、
**********************************
バス・オーダメイド旅行のご相談は…
銀のステッキ旅行
TEL 0797-91-2260(平日8:30~17:00)
■銀のステッキは会員制の「旅サロン」を主催しています。
■公式ホームページ:http://www.gin-st.com
**********************************