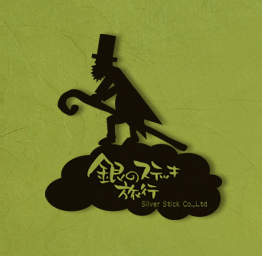秋田の夏、恐るべし ~西馬音内盆踊り~
「あんぱん、話の筋は好きやねんけど、歌がなぁ…」
朝ドラ見てますか?と訊いたときの、あるお客様の返事です。
「あぁ、あの歌」
たまにしか見ない私にもわかりました。
戦時中を描いたドラマにしては、やたらアップテンポで、込み入った作りの曲。
「速すぎて歌詞が聴きとれんのよねぇ」
「アーティストさんも大変ですよねぇ。
音符の数は決まってるのに新しい曲を作らないといけないんだから」
そんな会話を思い出したのは、秋田の小さな町で盆踊りを見ている時でした。
(キタカサッサ キタカサッサ フゥーウッ ドッコイナ)
ゆったりしたリズム。くりかえされる合いの手。
700年前から続くという西馬音内(にしもない)の盆踊りです。
まず驚いたのは、踊り手の半分ほどが真っ黒な頭巾で顔を隠していることです。
丸くふたつ、目だけ穴を開けた頭巾をすっぽり被った異様な姿は、
亡者踊りに由来しているのだとか。
残る半分、花笠の女性も半月型の編み笠を目深にかぶり、顔はまったく見えません。
〈踊る姿にゃ 一目でほれた 彦三頭巾で 顔しらぬ
(ソラ キタカサッサ ノリツケハダコデシャッキトセ〉
しなる指先の、うっすら汗ばんだ首筋の、なんとも言えぬ色っぽさ。
そうか、見せないことは、魅せることなのか(!)と気づいたり。
〈ホラ時勢はどうでも世間はなんでも 踊りコ踊らんせ(アーソレソレ)
日本開闢天の岩戸も 踊りで夜が明けた〉
(キタカサッサ キタカサッサ フゥーウッ ドッコイナ)
耳に染みついて離れない〈フゥーウッ〉の合いの手同様、踊りも同じ所作の繰り返し。
なのに、見飽きるということがまったくありません。
むしろ聴けば聴くほど、こちらまでトランス状態に入っていくようで…。
盆踊りが行われた秋田県の羽後町は、花火で有名な大曲の隣町でした。
より新しい色や形を追求する花火師が、
新曲を生み出そうと苦心するアーティストだとするならば、
西馬音内の盆踊りは、まるで対照的。
ヒトの原初的な部分に訴えてくるようです。
(人類学者の中沢新一が『チベットのモーツァルト』で描こうとしたように)
こんな対照的なふたつの祭りが、すぐ隣で受け継がれているなんて、
――秋田の夏、恐るべし、です。