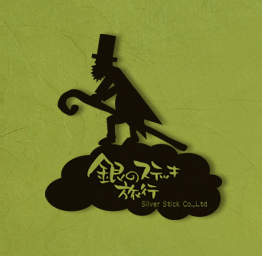生け花への淡い期待
「添乗員やっててよかった」
そう思うのは、旅先で本物に出会うことで新しい世界を知ったとき。
その反面、かつての職場の添乗先で、日々ほんものに出会っておきながら、
どうしても興味が持てなかったものがひとつ。
それは、花。
白状します。
日本全国・世界各地へ花追い旅をしながらも、
花の名前がなかなか覚えられません。
きれいだな、とは思います。
写真を撮ってみたりもする。
でも、顔(花)と名前が一致しない。
あやめと菖蒲のちがいは分かりません。
梅と桃は、ときどきあやしい。
自信をもって言えるのは、ひまわり、たんぽぽ、チューリップ
…って、これじゃまるで幼稚園。
歌舞伎役者や落語家の名前なら、師弟関係まですらすら言えるのに。
やはり興味がないということなんでしょう。
それでも添乗員たるもの、それぐらい知ってて当然と思われるようで、
信州のツアーに行くと必ずお客さまから聞かれます。
「これ、何ていう花ですか?」
さぁ……。
「じゃあ、あれは何ていう山ですか?」
…………。
なかには閉口して、こっそりこんな詩をつくっていた添乗員もおりました。
《 なぜあなたは聞くのだ あの山は何 あの花は何 》
まさかそこまで開きなおるわけにもいかないので、
自分なりに花に興味を持つべく工夫はしてみました。
あるときは、花木検定なるものを見つけ、
試験となれば嫌でも勉強するかも…と受けてみることに。
けれども結局、購入した参考書は放ったらかし。
そういえば受験生のときも、好きな科目しか勉強しなかったっけ。
またあるときは、花を育ててみようと思い立ち、
玄関前にプランターを並べ、チューリップの球根を植えてみました。
日々、成長をみることで、興味も愛情もきっとわくはず。
…なのに、何がいけなかったのでしょう。
春が来ても、背丈はふつうの半分ほど。
近所の子どもが数人のぞきこんでは、「このチューリップ、お病気かなぁ」
なんとかつぼみはつけましたが、悲しいことに開かないまま朽ちていきました。
以来、ご近所にも恥ずかしいし、子どもの情操教育にも悪いしで、
プランターはしまいこんだまま――。
今日、そんな私がめずらしく花に興味をもちました。
正確には、花ではなくて「生け花」に。
きのう完成したばかりのツアーの下見で、さっそく訪ねたある記念館。
生け花の家元のコレクションが展示されているということで、
ふだん、一般には非公開のところを特別に見せていただいたのです。
六甲の山あいにハッと目をひく重厚な建物の扉をくぐると、
なかは一転、アンデスの土着の世界。
仮面や壺など、大阪の民博を思わせるプリミティブアートの数々。
一瞬で、その世界にひきこまれました。
…すごい。
こんなところが近場にあるなんて全然知らなかった。
これならきっとお客さまも大感激のはず、と自画自賛しながらの帰り道、ふと。
こんなコレクションをする人の「生け花」って、どんなのだろう。
――今は亡きその家元は、古典偏重だった生け花の世界に
前衛を切り拓いた人物として知られるそうです。
生花を扱うため、作品の命はほんのつかの間。
写真集におさめられているというその生け花、
週末にも、図書館であたってみるとしましょう。
もしかすると今度こそ、花の魅力に目覚めるかもしれません。