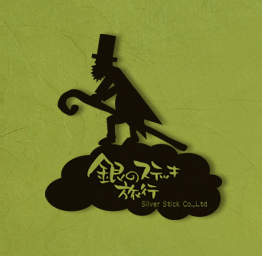If not forget ,is a guide for the future.
久しぶりに押入れから取り出した黄ばんだアルバム。
久しぶりには、訳があって、、、、
ものすごくパンパンに太っている若かりし自分を見たくない、
と、まあそんな単純な理由。
で、それなのに思い切って見た理由。
ある言葉を、もう一度、探したくって、懐かしいアルバムを繰りました。
今年の夏はいろんな意味で、戦後を思う夏でした。
多くの意見が、多くの場所から出るなかで、
私が思ったのは・・・
日本むかし話のこぶとりの爺さん(正直者)、ばかりでは
日本・ひとつの国は守れないのですね、ってこと。
鳩山さんが、土下座までして、お詫びする姿が
「おかしい」となる、それが大人の事情なのでしょう。
さて、残念ながら難しい話は私のキャパを越えるので・・・・
一般の、一人間の思い。
「戦争を知らない子供たち」なる歌がありましたが、
この対象は多分、60年~70年生まれを言うのでは、ないでしょうか。
どんぴしゃりの私。
中国残留孤児の帰還も毎年でした。
思えば、戦後が、意識しない中でも身近でした。
そして、小学校では、道徳の授業が毎週あって、
もとをただせば戦争に通ずる話がほとんでした。
小学校の高学年で担任になった先生は、
個人的に「ビルマの竪琴」の映画に感銘をうけて、
音楽の授業は、なんども「はにゅうの宿」を合唱させられました。
もちろん、「はだしのゲン」の映画は夏休み前のおきまりでしたし、
戦争を題材にした教育映画は、夏の授業の必須でした。
多分、戦争を知らない世代(我々)でしたが、戦後記憶が豊富な時代とあって、
語り部も現役ですから、今以上にリアルに、
そして過度に(現実そのまま)、戦争がどれほどのものか、
繰り返し教えていたように思います。
映像規制も平成に入ってのこと、
当時、小学生に見せるには過酷な映像があたり前でした。
原爆投下後のあまりに凄惨な映像を
「はだしのゲン」「ガラスのうさぎ」はまんま子供に語りました。
その後、大学生になると、
本多勝一の本が、ちょっとしたステイタスになって
(わたし的に)
「中国の旅」を読みました。
すぐ、森村誠一の「悪魔の飽食」も。
どちらも中国における日本人の犯した罪を題材にしたルポでした。
今は、ねつ造か、否かで常に話題にあがる、かの本です。
(その真意は歴史家に委ねるにてして)
少なからずこの本の影響で21歳の時に、
初めて中国を訪ねて、南京まで向かいました。
今でも覚えています。
南京大学に泊り、歴史的に日本が背負ったものを、
なんだか、自分たちが背負っているような気持ちで訪ねた南京の街。
「どこから来たの」と聞かれ、
その都度、少し間をおいて
「日本」と恐る恐る答えたことを思い出します。
正直怖かった。
でも、朝、南京大学の構内を出る時に流れていたのが、
忘れもしない、中国語で歌われる「万里の長城」、
そうチャゲ&飛鳥の歌でした。
その歌を背に、なんでしょう、
日中友好の懸け橋に、いま自分がなるんだ!
勇ましく、勝手に盛り上がっていたことを思い出します。
道に迷いながら目指した、博物館の途中。
出逢った村の人にお昼をご馳走になりながら、
「もしや、日本人とわかるなり石でも投げつけられるのでは」
そんな思いも杞憂に終わりました。
何度もキツイお酒で乾杯をさせられ、
もらい煙草も繰り返し、むせかえって涙も枯れた頃、
ようやく解放され、向かった南京博物館。
そこで見た「南京大虐殺」
私は、こう見ました。
戦争は、どのみち狂っているから、正論はどこにもない。
国を守るためと、政治的には、いろんな考えがあります。
もう世の中は、日本むかし話の太った方の爺さんばかりでないことを
知ってしまったのだから、それもしかたないと思います。
ただ、若い人に事実を知らせることは大事です。
オブラートに包まず、強烈に。
若い人は柔軟ですから。
知ってこそ、次が導ける。
私は、今ねつ造か否かと議論される「南京大虐殺」を信じて
ものすごい緊張感のなかでその場所へ出向きました。
日本人に初めて会ったという赤ら顔の、
当時はまだ人民服を着た村人に家でご馳走になり、
いいというのに、親切に博物館の場所にも同行してくれました。
そんな人々と別れた、数分後に見たものは・・・
結局、日本でも見てきた同じ、
戦争が生んだ鬼畜の産物があるだけでした。
いま、それが10だったか、100だったかと数が、議論されます。
国を守る、それには、たぶん必要なのでしょう。
簡単に謝ってもいけないし、事実は、きちんとしないといけない。
でも、どうであれ傷ついたことの事実は互いに平等です。
これを知ることがすごく大事と思います。
お膳立てされて知ったことと、
現地で知ることの差違もしかり。
あの優しかった村人は今どうしているでしょうか。
私が、どうしても思い出したかった、20数年前に写真に残した
フレーズが、これです。
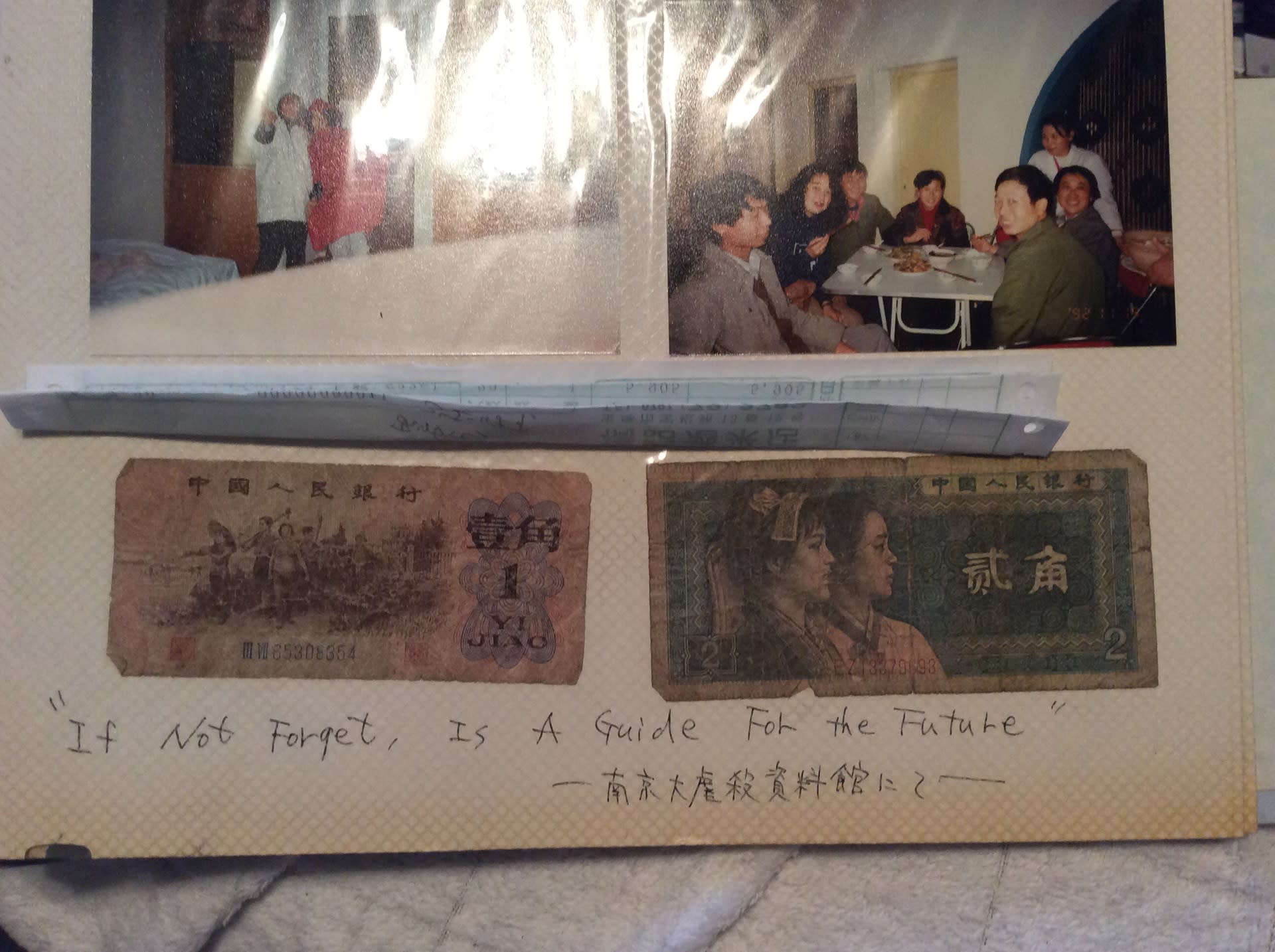
あの時、20数年前は、分かり合える日が近いと思っていました。
きっと未来は来るものと思っていました。
博物館の出口に大きく掲げられていた、この言葉。
いまどこを向いているのでしょうか。
*************************************
貸切バス・オーダメイド旅行のご相談は…
銀のステッキ旅行
TEL 0797-91-2260(平日8:30~17:00)
■銀のステッキは会員制の「旅サロン」を主催しています。
■公式ホームページ:http://www.gin-st.com
**************************************